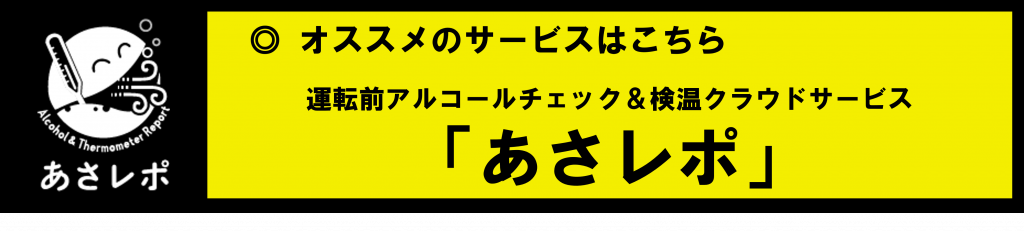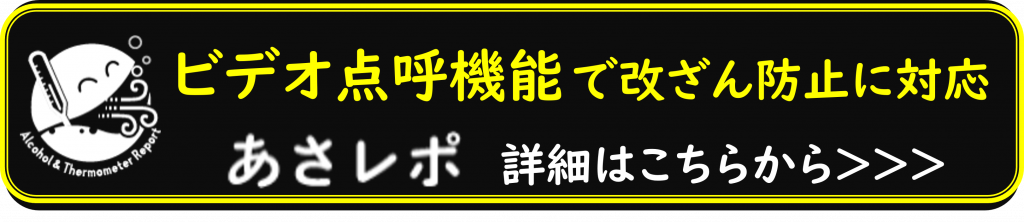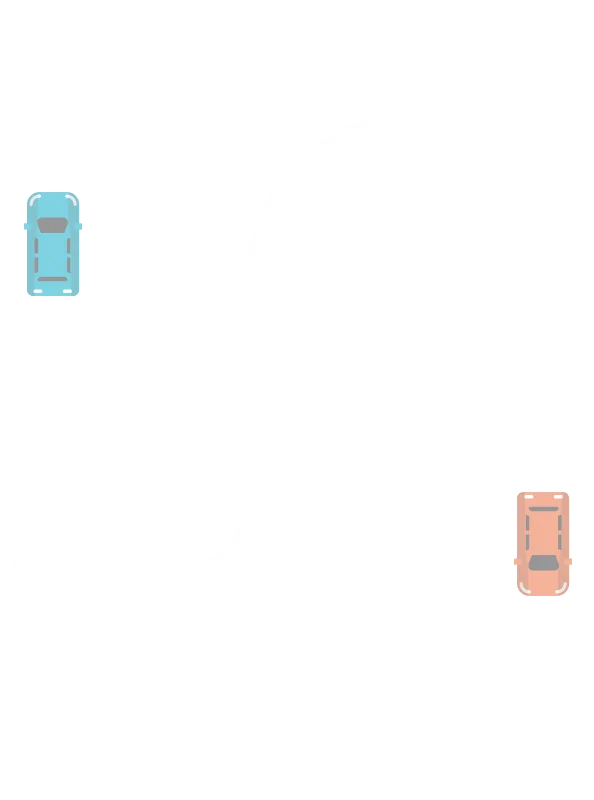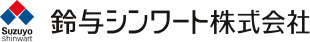クラウド型アルコールチェックサービスの見直し時期と課題整理
近年、飲酒運転やアルコールチェックに関する法規制は一層厳格化し、企業には確実な管理体制が求められるようになりました。これに伴い、多くの企業がクラウド型アルコールチェックサービスを導入しました。
サービス導入を急ぐあまり、とりあえず法令対応を急ぐことが目的になり、サービスが自社に適しているかなど、しっかり検討せずに導入をしてしまったケースが多く見受けられます。
機能の十分さよりも「すぐに使えるか」や「導入コストを抑えられるか」といった観点でサービスを選んだ企業も少なくありません。
しかし、導入から時間が経つにつれ、現場の利便性や法規制の変化などにより、導入したサービスでは対応しきれない課題が表面化してきたのではないでしょうか?
「今のサービスのままで本当に大丈夫か」「より良い選択肢があるのではないか」と、アルコールチェックサービスの見直しや乗り換えを検討するタイミングを迎える企業が増えています。
本コラムでは、適切なアルコールチェックの実施と正しい管理体制の観点から、現場での課題を整理し、乗り換えの判断基準やサービスを選ぶ際の注意点などを紹介します。
アルコールチェック義務化のおさらい
はじめに、アルコールチェック義務化についての法令をおさらいしましょう。法令は随時追加されており、正しい情報を把握していなければ利用中のサービスが適切であるか判断できません。現時点(2025年9月)で警察庁から発表されているアルコールチェックにまつわる法令を整理しましょう。

2022年4月1日、安全運転管理者を選任している一定規模以上の事業所において「運転者の酒気帯びの有無を運転前後に目視で確認し、そのデータを1年間保存すること」が義務付けられました。
続いて、2023年12月1日からは、「アルコール検知器を使用したアルコールチェック」が義務化され、より厳格な確認方法が求められています。
この義務は、日常的に運転業務を行っている従業員だけでなく、週に数回や月に数回運転する従業員に対しても等しく適用されます。
原則として、運転前後に対面での目視確認と、アルコール検知器を用いたアルコールチェックを行うことが求められています。もしドライバーが遠隔地にいるなどの理由で対面確認が困難な場合には、携帯型のアルコール検知器を使用し、電話やビデオ通話などの手段で、管理者が立ち会う方法で代替することも可能です。
また、アルコール検知器の日常的な点検とメンテナンスも義務化項目です。具体的には、電源が入るかの確認や、正常時の呼気を使って正しい数値が測定できるか、アルコールを含む呼気に対してきちんと反応するかなどの定期的なチェックです。
アルコールチェックの結果は、紙の記録簿または、デジタルデータとして、1年間保存することが義務付けられています。アルコールチェックの記録は万が一の事故発生時や監査対応の際に必要なため、整備された管理体制のもとで、確実に保管する必要があります。
現場でよくある課題
当初はアルコールチェックさえできれば十分だと考えて導入したサービスでも、使い続ける中でいろいろな問題が出てきています。たとえば、本当に法令遵守できているのかという不安、管理の手間やコスト面などさまざまです。
こうした問題をそのままにしておくと、行政からの指導や法的なトラブルにつながるだけでなく、日常のチェックが形だけになり、管理体制への信頼を失う危険があります。
ここからは、多くの企業で共通して見られる課題と、アルコールチェックサービス再選定の際に意識したいポイントを整理します。
課題1 法令遵守への不安
アルコールチェックの義務化以降、事業者には厳格な管理体制が求められています。道路交通法施行規則では、運転前後のアルコールチェックと記録の保存が義務付けられ、さらにその記録は正確で改ざんされていないことが前提です。保存期間は1年間と定められており、管理者はいつでも確認できる状態にしておく必要があります。
法令に対応できていない場合、企業は重大なリスクを負うことになります。実際に大手配送事業者がアルコールチェックの不備を理由に行政処分を受けた例もあり、遵守体制の甘さで企業の信用を大きく損なう可能性があります。
特に注意すべきなことは、なりすましや記録の改ざんといった不正です。アルコールチェックをした記録が残っていても、実際には本人確認ができていなかったり、後から記録が改ざんされていたりすれば、法令違反に留まらず、事故発生時には管理体制そのものが否定され、企業責任を厳しく問われることになります。これは絶対にあってはならない事態です。

導入済みのアルコールチェックサービスが、こうしたリスクにどこまで対応できているのかを改めて確認する必要があります。最新の法改正や規制強化に確実に適応でき、顔認証や改ざん防止機能などで不正を防げる仕組みを備えたサービスの導入を検討することは、企業にとって必須の取り組みです。
課題2 利便性とコストのバランス
法令遵守しているだけで十分とはいえません。アルコールチェックをするドライバーの操作が複雑だったり、管理者の記録確認に手間がかかるようでは、現場に負担がかかり、いずれはアルコールチェック忘れや、チェック漏れにつながります。利便性が高いサービスであれば、それらの防止につながり、結果的に法令遵守の徹底にも役立ちます。
また、クラウド型アルコールチェックサービスを導入すれば業務効率は向上しますが、コストが見合うかという課題があります。コスト削減のために一部は紙で管理し、他はクラウドサービスで管理する「二重管理」が発生すると、管理者の負担はかえって増大します。場合によっては、どの記録が正しいのか分からなくなる危険性もあります。
だからこそ、利便性とコストの両立が欠かせません。たとえば、従量課金制度のアルコールチェックサービスを利用することで、頻繁に運転しない従業員の管理を低コストで運用でき、二重管理を避けることが可能となります。ドライバーに負担がかからず導入できて、かつ企業全体として統制のとれた管理ができるサービスを選ぶことが、今後の安定した運用のカギとなります。
課題3-1 乗り換えにかかる負担
アルコールチェックサービスを乗り換える際には、想像以上の負担が担当者にのしかかります。過去データを安全に移行しなければ、監査対応や万一の事故調査の際に必要な記録が失われるリスクがあります。また、従業員に対して新しい操作方法を教育したり、既存の業務フローに合わせて運用を再構築したりといった作業も必要です。これらは一つひとつが手間であり、担当者にとっては大きな負担となります。

さらに、計画的な移行管理を行わずに導入してしまうと、社内での混乱や誤った運用が発生しやすくなり、結果的に「法令遵守のための導入」が逆にリスクを生むことにもなりかねません。
だからこそ、単にシステム導入するだけでなく、教育や運用フローに合わせたチューニングを支援してくれる、サポート体制のあるサービスを選ぶことが重要です。導入検討段階から現場に寄り添うサポートがあるかどうかが、スムーズな乗り換えの成否を分けます。
課題3-2 サポート体制
クラウド型アルコールチェックサービスを継続的に安定して運用するためには、サービス提供元のサポート体制が非常に重要です。導入直後だけでなく、運用を進める中で必ずトラブルや疑問は発生します。その際に迅速かつ適切なサポートが得られなければ、業務に大きな支障をきたす場合があります。
たとえば、システム障害やデータ不具合が発生した際、サービス提供元の対応が遅いかったり、問い合わせをしても十分な回答が得られない場合などは、現場は混乱し、トラブルが長引き、結果的に「法令遵守のための管理」が滞るリスクが高まります。サポートが不十分であると、利用者自身が問題解決に追われ、本来の業務に専念できなくなります。
このような状況を避けるためには、導入前に提供元のサポート体制を見極めることが大切です。専用のサポート窓口や迅速な対応体制が整っているか、また現場の運用に合わせたアドバイスをしてくれるかどうかは、サービス選定の大きな判断基準となります。もし現在利用しているアルコールチェックサービスのサポートに不満がある場合は、より手厚い支援を提供するサービスへの乗り換えを検討することが、業務効率の向上と法令遵守の徹底につながります。
課題4 セキュリティとシステム信頼性
アルコールチェックをした際に取得するデータには、氏名や顔写真などの個人情報が含まれます。そのため、サービスのセキュリティ対策や個人情報管理は非常に重要です。導入を検討する際には、ISO認証など第三者による基準に適合しているかを確認する必要があります。
セキュリティが不十分なサービスを利用すれば、データ漏洩や不正アクセスによって企業の信用失墜や法的問題につながる可能性があるため、乗り換えの際には、信頼できる環境・管理体制を備えたサービスを選ぶ必要があります。
さらに、システムトラブルが頻発するサービスや、法令改正に合わせてアップデートをしないサービスを使い続けると、業務の停滞や法令違反のリスクにつながります。機能の柔軟性や拡張性が乏しい場合も、将来的な業務改善や業務効率化の足かせになりかねません。
セキュリティとシステムの安定性は、サービス乗り換えを検討する大きな理由のひとつです。安心して利用でき、長期的に信頼できるサービスを選ぶことが、企業にとって不可欠な条件といえるでしょう。
「あさレポ」で課題をまとめて解決
これまで挙げてきた4つの課題(法令遵守への不安、利便性とコストのバランス、サービスを乗り換える際の負担、サポートやシステムの信頼性)すべてを一度にカバーするのは容易ではありません。
鈴与シンワートが提供する「あさレポ」は、こうした課題を総合的に解決できるクラウド型アルコールチェックサービスです。顔認証や改ざん防止などの法令遵守に対応する機能、ドライバーが使いやすいアプリの操作性、管理者の負担を軽減する運用サポート、さらに高いセキュリティ基準に対応したデータ管理環境を備えています。
導入後もドライバーに負担をかけず、業務効率の向上と法令遵守を両立できる仕組みが整っているため、サービスの乗り換えを検討する企業にとって安心です。
「アルコールチェックサービスの見直しと課題整理」まとめ
法改正に伴ってクラウド型アルコールチェックサービスを導入しても、実際の運用や法規制の強化など、常に最適であるかを慎重に検討する必要があります。法令遵守や記録の正確性、ドライバーか利用するアプリの使いやすさ、コスト、サポート体制、セキュリティとシステムの信頼性など、見落とせないポイントは多岐にわたります。
これらの課題を放置すると、法的リスクや現場運用の混乱、業務効率の低下につながる可能性があります。だからこそ、サービスの見直しや乗り換えは、企業の安全性と効率性を高めるための重要な判断です。
「あさレポ」は、これらの課題を総合的にカバーできる仕組みを備えています。あらゆる変化に対応し、利便性と確実性を追求し続けているサービスです。法令遵守、運用の利便性、管理負担の軽減、そして高いセキュリティと安定したシステムを兼ね備え、企業のアルコールチェック運用を安心かつ効率的に支援します。
すでに導入したアルコールチェックサービスの運用に不安を感じる企業にとって、安全で確実な管理体制を実現するために「あさレポ」への乗り換えは、有力な選択肢です。
「あさレポ」は、安全運転管理者に役立つ機能や管理業務のサポートに力を入れています。
無料トライアルもできますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。