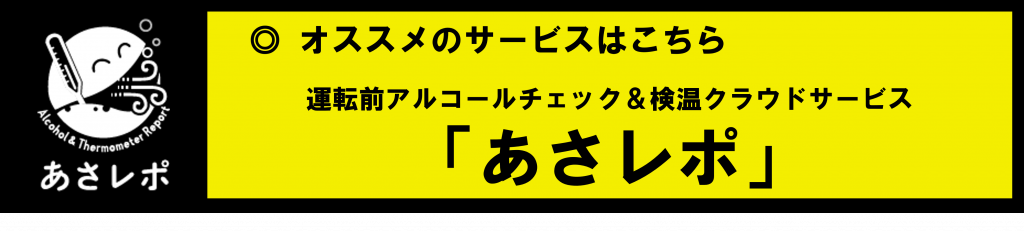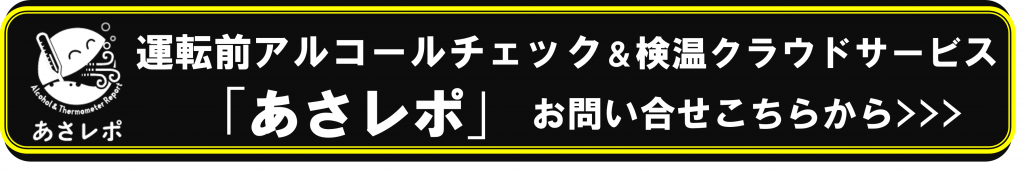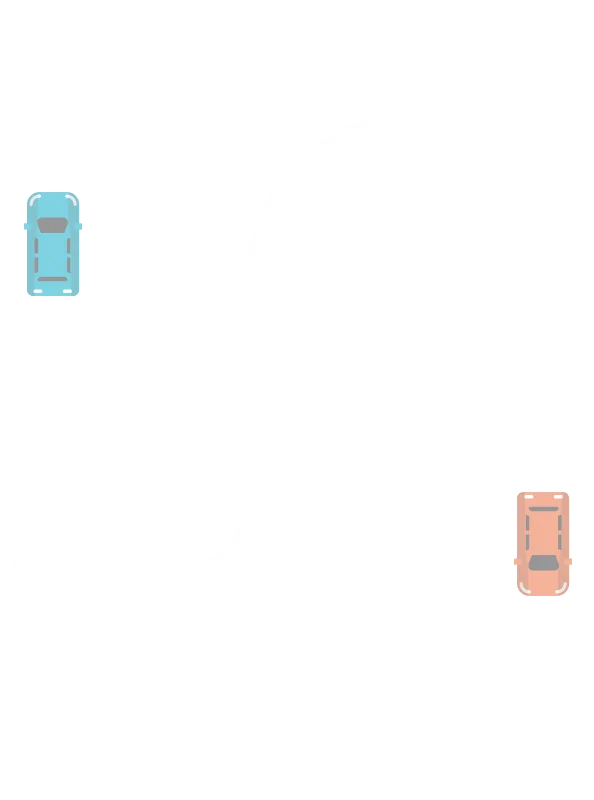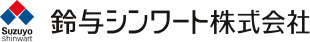普段、運転しない人こそ要注意!アルコールチェック管理はクラウドサービスにお任せ!
安全運転管理者にとって、業務で車を使用する従業員のアルコールチェックは重要な管理項目です。中でも運転頻度が低い従業員、いわゆる「時々運転する人」の管理を見落としたり、対応が後回しになるケースが少なくありません。毎日運転する従業員と異なり、運転予定が直前に決まる場合や、運転頻度が少ないために記録方法が簡素化されるケースなども多く、アルコールチェックを忘れたり、記録の不備が発生しやすい状況にあります。
しかし法令では、運転頻度にかかわらず、運転前後のアルコールチェックとそのデータの記録保存が義務付けられており、すべての運転者を対象とした管理体制の整備が企業に求められます。「時々運転する人」のチェックも確実に実施し、かつ運用の負担を最小限に抑えることが重要になります。
本コラムでは、データを管理する上で見落とされがちなリスクや課題を整理し、その解決策としてクラウドサービスを活用した柔軟かつ効率的な運用方法を紹介します。
アルコールチェック義務化のおさらい
アルコールチェックのデータを管理することは、運転の頻度にかかわらず、業務で車を使用するすべてのドライバーに求められています。
特に運転頻度が少ない従業員のアルコールチェック記録・管理は曖昧にされがちですが、企業は法令を遵守し、従業員に安全な運転をさせるためには、運転頻度にかかわらず、確実な管理体制を整える必要があります。
2022年4月1日からは、安全運転管理者を選任している一定規模以上の事業所において「運転者の酒気帯びの有無を運転前後に目視で確認し、そのデータを1年間保存すること」が義務付けられました。
さらに、2023年12月1日からは、「アルコール検知器を使用したアルコールチェック」が義務化され、より厳格な確認方法が求められています。
この義務は、日常的に運転業務を行っている従業員だけでなく、週に数回や月に数回運転する従業員に対しても等しく適用されます。
原則として運転前後に対面での目視確認と、アルコール検知器を用いたアルコールチェックを行うことが求められています。もしドライバーが遠隔地にいるなどの理由で対面確認が困難な場合には、携帯型の検知器を使い、電話やビデオ通話などの手段で、管理者が立ち会う方法で代替することも可能です。
また、アルコール検知器の日常的な点検とメンテナンスが必要です。具体的には、電源が入るかの確認や、正常な呼気を使って正しい数値が出るか、あるいはアルコールを含む呼気に対してきちんと反応するかなどの定期的なチェックです。
そして、アルコールチェックの結果は、紙の記録簿あるいはデジタルデータとして、1年間保存することが義務付けられています。アルコールチェックの記録は万が一の事故発生時や監査対応の際に必要なため、整備された管理体制のもとで、確実に保管する必要があります。
このように、アルコールチェックの義務は「たまに運転するだけだから」という理由で省略できるものではありません。アルコール検知器の適切な運用と、アルコールチェックデータの保存体制を含めた一連の管理を、すべてのドライバーに行うことが、企業のリスクマネジメントの基本となります。
運転頻度が低い従業員の管理課題
運転頻度が低い従業員の場合、運転前後のアルコールチェックのタイミングが不規則になりやすく、確認や記録を忘れやすいという問題があります。特に直行直帰や出張などで対面確認が難しいケースでは、遠隔での確認体制を整備しないと、チェックが甘くなり、管理の精度が下がります。
また、アルコール検知器の測定結果をごまかす不正行為のリスクも大きくなります。普段から運転しない従業員は、検知器の操作に不慣れなことが多く、不正防止機能がない機器を使用すると不正が起こりやすくなります。このため、不正防止機能付きの機器を導入することが重要です。
運転頻度が低い従業員のアルコールチェックデータはコストや作業負担を軽減するために、記録を紙の台帳で管理する傾向にあります。紙管理とクラウドサービスの二重管理をすると、作業負担が増加したり、データ管理の正確性が欠如しやすくなります。これらの課題を踏まえ、効率的で確実な管理方法の検討が必要です。
運転頻度が低い従業員のアルコールチェック管理は、後回しにされがちですが、企業の安全運転管理体制を維持するために欠かせない重要なポイントです。次章では、こうした課題を解決する具体的な方法について詳しく解説していきます。
クラウドサービス「あさレポ」で解決する4つのポイント
たまにしか運転しない従業員に対して確実なアルコールチェックとデータ管理をするには、従来の対面や紙ベースの運用だけでは限界があります。
そこで有効なのが、運転前アルコールチェック&検温※クラウドサービス「あさレポ」の活用です。具体的な課題とその解決策をわかりやすく紹介します。
※ 鈴与シンワート指定の検温機能付きアルコール検知器利用時に検温が可能です。
1. アルコールチェック忘れや不正を防ぐ「クラウドサービスでの確実な実施とデータ保存」
「あさレポ」は、アルコールチェックを確実に行い、その結果を安全かつ正確に管理するための仕組みを提供します。
AI顔認証ログインを採用しているため、アプリ起動時には本人確認を確実に行い、代理測定やなりすましといった不正行為を防止します。また、アプリはシンプルな画面で直感的に操作できるため、使用頻度が少ない方でも迷わずに使用できます。測定が完了すれば、その結果は改ざんできない形で自動的にクラウドサーバに送信され、計測データはすぐに管理者が確認できます。加えて、通知機能により、チェックの実施を忘れている場合にリマインドされるため、アルコールチェック忘れの防止にもつながります。
2. 必要なときだけ使える「従量課金制」でコストの最適化
普段あまり運転しない従業員にユーザーアカウントを毎月用意すると無駄なコストがかかります。「あさレポ」は、使用した日数分だけ料金が発生する従量課金制と月額料金制をユーザーごと、月ごとに選択できるため、実際に使用した分の費用負担で済みます。

たとえば、稀に運転する従業員が人手不足や急なシフト変更などで運転をした月は運転した日数分の請求、一度も運転しなかった月は料金が発生しないといった風に毎月調整できます。こうした柔軟な料金体系により、必要なときだけしっかり管理し、無駄のない運用が可能になります。コスト面で導入をためらっていた企業にも、現実的な選択肢となるでしょう。
3. 遠隔地でも対応可能な「ビデオ点呼機能」で確実な管理体制を構築
直行直帰や出張を含む運転の際、アルコールチェックの対面実施が難しくなります。「あさレポ」は、ビデオ通話を活用したビデオ点呼機能を備えており、遠隔でも運転前後の確認を確実に行うことができます。リアルタイムで相手の様子を確認しながら遠隔地からの対面点呼ができるため、紙や画像による報告と比べて信頼性が格段に高く、運転頻度の低い社員に対しても一貫したチェック体制を整えることができます。
4. 車両点検や走行記録の見える化で、管理の手間とばらつきを軽減
業務で運転をする頻度が少ない従業員は、アルコールチェックに不慣れなため、車両点検の確認項目や走行記録の記入が正しくできず、記録ミスや漏れが発生しやすい傾向にあります。
「あさレポ」の運転日報オプションは、車両点検項目が画面上にシンプルに表示され、チェックすべき内容が一目で分かります。さらに、GPSによるルート記録機能により、走行距離が自動で算出されるため、ODOメーターの読み忘れや記録ミスを防ぐことができます。こうした仕組みにより、誰が運転しても一定の水準で点検・記録を行える体制が整い、紙での記録にありがちな属人化や記録精度のばらつきも解消されます。
このように、「あさレポ」は運転頻度が低い従業員に対するアルコールチェック管理の課題を、制度面・運用面・コスト面から総合的に解決できるクラウドサービスです。運転頻度が低いと、チェックの抜けや管理の負担が発生しやすくなります。だからこそ、仕組みでしっかり支えることが大切です。クラウドサービスを活用すれば、無理なく、確実に、安全運転の体制を整えることができます。
「時々運転する従業員」のアルコールチェック管理 まとめ
アルコールチェックは、運転頻度に関わらず、対象となるすべてのドライバーに対して実施が義務付けられています。たとえ月に数回の運転であっても、「たまにしか乗らないから」という理由で確認がおろそかになっては意味がありません。運転の機会が少ないからこそ、仕組みやツールを活用して、確実なチェック体制を整えておくことが大切です。
クラウドサービスを取り入れることで、アルコールチェック忘れや記録ミス、不正のリスクを未然に防ぐことができます。特に、遠隔地からの確認や、なりすまし防止の認証機能、分かりやすい操作手順、そして必要なときだけ課金される柔軟な料金プランなどは、運転頻度の低い社員を管理する場面で非常に有効です。
あまり運転しない従業員のアルコールチェック管理には、クラウドサービスの活用が最適です。管理者の負担を減らしつつ、事故を防ぐ。その第一歩が、確実なチェックと記録の仕組みづくりです。
鈴与シンワートの「あさレポ」は、安全運転管理者に役立つ機能や管理業務のサポートに力を入れています。ぜひお気軽にお問い合わせください。