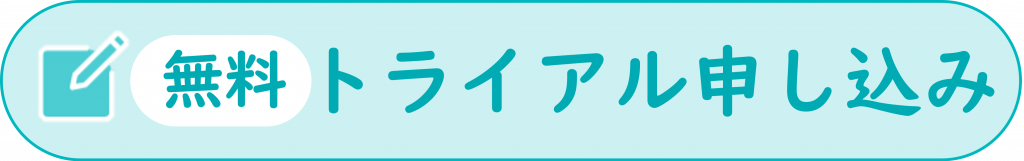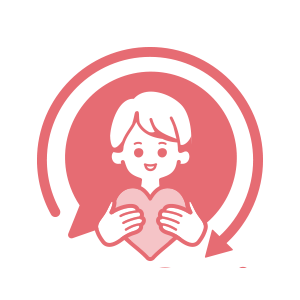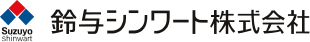医療現場の離職を防ぐには?離職の背景と対策を徹底解説!
医療現場では、日々1人ひとりの患者に向き合いながら、責任ある判断と迅速な対応が求められています。看護師をはじめとする医療従事者は、常に緊張感のある状況下で働いています。
そうした現場を支える人材の確保と定着が、大きな課題となっています。人手不足が慢性化する中、スタッフの離職が相次ぐ状況は多くの医療機関に共通する悩みです。育成しても辞めてしまう、採用しても定着しない。こうした声は後を絶ちません。
医療従事者の離職には、さまざまな背景があります。過重労働や夜勤を含む不規則な勤務、人間関係のストレス、そして家庭との両立の難しさなど、日常的な負担の積み重なり、離職を選択するスタッフが増えています。
特に問題なのは、悩みを抱えたスタッフが、誰かに相談できずに、はたから見たら突然の退職となるケースです。業務責任の重さと忙しさ、人手不足に加え、自分のつらさを伝えられない環境が、相談のきっかけを奪っている可能性があります。
本コラムでは、医療従事者の離職が多い理由を紐とき、どのような対策が必要なのか具体的に紹介します。
目次
医療従事者の離職率
厚生労働省が発表した統計※によると、全産業の離職率は15.0%で、医療・福祉分野の離職率は15.3%と他産業と比べて若干高い傾向にあります。令和4年度の産業別の入職と離職のグラフを見ると、医療・福祉の分野は入職者が1138.1人に対し、離職者が1210.0人と入職者を上回る結果となっています。
このデータから、医療現場では結果的に「入職者が多くても離職者も多い」構造が続いており、採用だけでなく定着支援の必要性が強く示唆されます。
※参考:厚生労働省「令和4年雇用動向調査結果の概要」産業別の入職と離職
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/koyou/doukou/23-2/index.html
また、日本看護協会「2024年 病院看護実態調査」の2023年度の調査※によると、
正規雇用看護職員の離職率:11.3% 新卒採用者の離職率:8.8% 既卒採用者の離職率(採用した年度内に離職した割合):16.1% |
に達しています。この数値からも、特に既卒看護師の離職率が高く、再就職や転職のために離職する傾向にあることが分かります。加えて、この調査で看護管理者が考える退職した新卒看護師の主な退職理由として「健康上の理由(精神的疾患)」が52.5%ともっとも多い理由でした。
また、看護職員としての適性や上司・同僚との人間関係なども上位に挙がっています。このことから、医療の現場での「医療従事者のメンタルヘルスの支援」は重要な課題であることが分かります。
※参考:日本看護協会「日本看護協会調査研究報告 <No.101> 2025 2024年 病院看護実態調査報告書」
https://www.nurse.or.jp/nursing/assets/101.pdf
医療従事者が退職する主な理由
医療従事者の離職には、個人の事情だけでなく、職場環境や制度設計などへの不満が重なることが原因になることが多々あります。ここでは、医療現場で特に多く見られる主な退職理由を4つ紹介します。
過重労働や長時間労働による負担
医療現場では、緊急対応や夜勤が日常的に発生し、勤務時間が不規則になりやすい傾向にあります。
特に緊急度や重症度が高い患者に対応するために、高度かつ専門的な治療が行う環境を備えた「急性期病院」などでは、交代制勤務に加えて突発的な残業が続き、心身の疲労が蓄積しやすくなります。
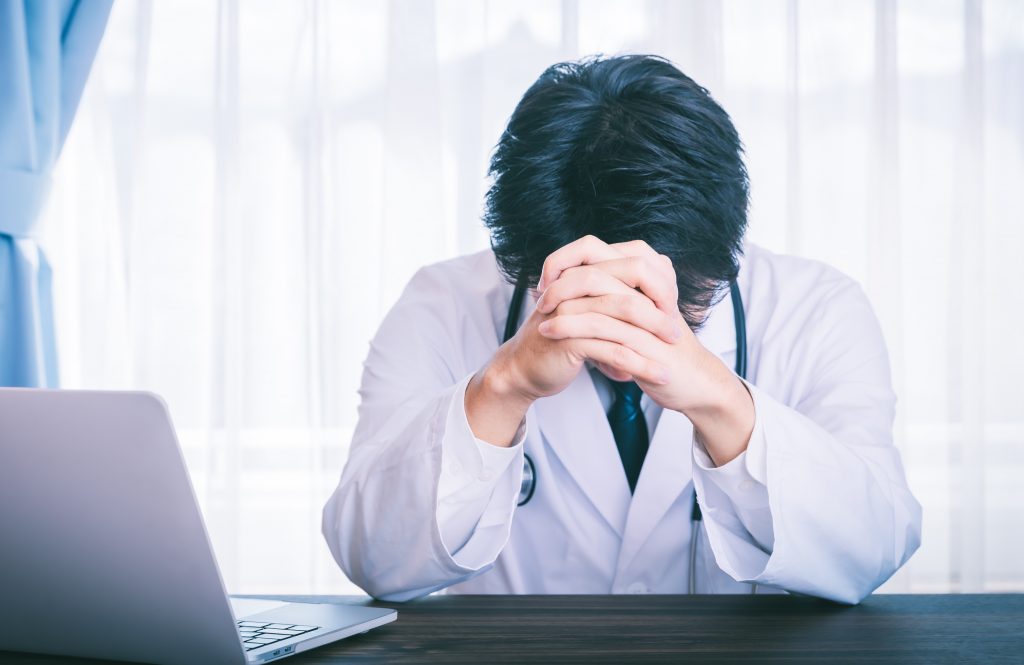
医療従事者への負担は、身体的な負担だけではありません。事務作業や患者の家族への対応、院内会議など、患者ケア以外の業務も多く、慢性的な業務過多に悩むスタッフも多く存在します。
このような状況が解消せず長引くことで、体調不良などをきっかけに離職を選ぶ結果につながることがあります。
人間関係やコミュニケーションの難しさ
医療の現場では、医師や看護師、介護職員、事務スタッフなど、さまざまな職種のスタッフが関わり合いながら働いています。それぞれの立場や役割が異なるため、価値観や考え方にズレが生じることもあり、うまく意思疎通ができない場面もあります。
また、同じ職種でも、経験年数や年代、働く目的の違いなどから、同僚や上司との関係性に悩むことや、仕事のやり方やコミュニケーションスタイルが合わず、ストレスに感じることがあります。
こうした悩みを感じても、気軽に話せる相手がいない、相談できる場がないという方も多いのではないでしょうか。
言いにくい人間関係の不満は、1人で抱えていると次第に大きなストレスとなり、心の負担が限界を超えた時に、突然の離職につながることがあります。
給与や待遇面への不満
医療従事者は、高い専門性と責任を求められる仕事であるにもかかわらず、それに見合う報酬が得られていないという不満は根強く存在しています。特に地方や小規模病院では、給与水準や賞与、手当の面で都市部との格差を感じる場合があります。
また、昇給やキャリアアップの道筋が不明瞭であることも、将来への不安や職場への不信感につながります。目に見える評価や処遇が伴わなければ、努力を続ける意欲を保つことが難しくなります。
ワークライフバランスや家庭との両立の困難さ
子育てや介護など、家庭の事情と仕事の両立に悩む医療従事者も多く存在します。特に夜勤や長時間勤務が求められる環境では、家事だけでなく、保育園の送り迎えや家族のサポートとの両立が困難になりがちです。
育児や介護などのライフイベントに対する制度が整っていなかったり、制度はあっても職場の理解が得られず、利用しにくい場合もあります。このようなことから、休暇が取りづらい職場環境の中、家庭を優先するために退職を選択せざるを得ないケースがあります。
医療従事者のための離職対策
医療現場での離職を防ぐには、スタッフ個人の努力や我慢に頼るのではなく、組織としての仕組みや制度の見直しが必要です。この章では、病院が取り組むべき具体的な対策を3つの観点から見ていきます。
勤務体制と業務負担の適正化
医療現場では、突発的な業務や夜勤対応などが発生しやすく、勤務が不規則になりがちです。しかし、単にシフトを調整するだけでは、根本的な解決にはつながりません。休みが取りにくい背景には、人員配置の偏りや、1人が抱える業務量の多さが影響している場合もあります。たとえば、限られた人数で多くの業務を回さなければならない状況では、休みたくても代わりの人員が見つからず、結果として休暇取得を遠慮する雰囲気が生まれてしまいます。
こうした負担を軽減するためには、まず業務の棚卸しを行い、属人化している業務や非効率な業務などを見直すことが効果的です。
また、ICTや業務支援ツールの導入も効果的です。データ記録や情報共有の工数を削減し、正確なデータを一元管理することはスタッフの業務時間や心の余裕につながります。
勤務体制の改善は、一時的な対応ではなく、長期的に働き続けられる環境を整えるうえで、不可欠な土台となります。
処遇やキャリア支援の整備
適切な給与や評価制度は、働く意欲を向上させる大きな要素です。専門性の高さに見合った報酬や手当が支払われているかを定期的に見直すとともに、スタッフの努力や成果がきちんと認められる仕組みを整えることが大切です。
また、キャリアパスの提示や、スキルアップの支援も重要です。将来に希望が持てる環境であることが、働き続けるかどうかの判断につながります。役割や経験に応じた研修や資格取得のサポート体制があることで、スタッフの定着率は大きく向上します。
育児や介護と両立できる柔軟な制度設計
ライフステージの変化に応じた柔軟な働き方の実現は、離職を防ぐ上で欠かせません。育児や介護など、家庭の事情と両立できるよう、時短勤務や日勤中心のシフト、フレックス制度などを導入することが求められます。
さまざまな休暇取得制度があっても実際に利用しづらいという声が上がる場合は、職場全体の意識や風土の改善が必要です。管理職が率先して制度活用を後押しし、働き方の多様性を認め合える文化を育てることが、結果的に組織全体の安定につながります。
このように、離職防止のためには、現場の声に耳を傾けながら制度の導入と運用できる環境を整えていくことが重要です。
離職防止対策におすすめの従業員エンゲージメント向上支援サービス「ここレポ」
医療現場の離職を防ぐには、制度や人員配置といった構造的な改善だけではなく、日々の「気づき」がカギになります。
特に忙しく張りつめた現場では、スタッフが不調や不満を自ら言葉にするのは難しく、同僚や上司へ相談することなく離職の意志が固まっていることも少なくありません。
だからこそ、自然に気づける仕組みづくりが重要です。その仕組み作りに有効なツールが、スタッフのエンゲージメント向上を支援するサービス「ここレポ」です。
業務の合間にできる簡単サーベイ
「ここレポ」は、スタッフが出退勤時に、スマートフォンやタブレット、PCを使用して簡単なサーベイに回答するサービスです。
体調や気分、業務への気持ちを数秒で記録できるため、ナースステーションや更衣室など、日々の動線の中で無理なく、気軽に取り入れられる点が特長です。
定時報告ではなく、自分のペースで入力できるため、スタッフにとっても心理的なハードルが下がります。
AI表情分析で、言葉にできない心の変化を察知
医療従事者の多くは、「周囲に迷惑をかけたくない」「大変なのは自分だけじゃない」と考え、不調や不満を言葉にすることをためらいがちです。
「ここレポ」は、勤務前後に撮影した画像の表情もとにAIが感情の変化を分析し、スタッフ本人も気づいていない小さな違和感やストレスの兆候を数値化します。
言葉にしなくても心の変化が伝わる仕組みによって、本音を言えない現場でも変化を早期にキャッチすることが可能です。
管理者の負担を減らし的確にフォロー
看護師長や管理者にとって、全員の体調やメンタルを日々気にかけることは容易ではありません。
「ここレポ」は、個人ごとの状態変化をダッシュボード上で一覧化します。異変があった時にはアラート通知があるため、管理者は負担を増やすことなく、必要なタイミングで必要な人に寄り添うことができます。
「気になっていたけど声をかけそびれた」という後悔を、仕組みで減らすことができます。
不満をため込ませないための報告機能
さらに、「ここレポ」には自由記述型の報告機能があり、スタッフがちょっとした不満や違和感、人間関係のストレスなどを気軽に吐き出せる場としても活用できます。
報告は匿名や非公開でも投稿可能なため、「誰にも言えなかったこと」をため込まずにつぶやき感覚でアウトプットでき、離職の引き金になり得る小さな不満を、早期にキャッチすることが可能です。
「医療現場の離職率が高い背景と対策」のまとめ
医療従事者の離職を防ぐためには、待遇や制度面の見直しに加え、日々の小さな変化にいち早く気づき、適切に対応できる体制を整えることが重要です。特に多忙な医療現場では、スタッフの不調や不満が表面化せず、結果的に対応が遅れることが課題となっています。
「ここレポ」は、勤務前後のサーベイやAIによる表情分析を通じて、スタッフの状態を可視化し、管理者のフォロー判断を支援する従業員エンゲージメント向上支援サービスです。加えて、報告機能を活用することで、日常のちょっとした悩みや不満も蓄積させることなく離職のリスクを軽減します。
現場の忙しさや人間関係のストレスが離職につながる前に、個々の変化に気づき、スタッフの声を受け止める仕組み作りをすることが、安定的な人材確保と職場定着のカギとなります。
鈴与シンワートの従業員エンゲージメント向上支援クラウドサービス「ここレポ」は、医療現場の管理者に役立つ機能や業務サポートに力を入れています。ご相談やお見積りも対応可能です。お気軽にお問い合わせください。