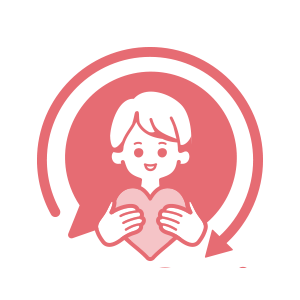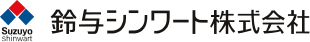【人事向け5月病対策】5月に増える「人材流出」の理由と離職防止対策
「なんとなく元気がない」「会話が減った」「表情が硬い気がする」――
ゴールデンウィーク明けの職場で、同僚や後輩のちょっとした違和感に気づいたことはありませんか?
5月は、1年の中でも特に従業員の心身に変化が現れやすい時期です。4月の新年度を乗り越えた安心感の裏で、実は疲労やストレスが蓄積していたり、環境の変化に順応できずに悩んでいたりする人も少なくありません。
表面上は分からなくても、内面では不調の前兆が出ているケースは意外と多くあります。その不調が連休の気持ちが緩んだタイミングで、一気に表面化することがあります。
こうした小さな変化は、組織の中では見逃されがちです。本人が声をあげない限り、まわりが気づくことは難しく、気づいた時にはすでに退職の意志が固まっていた、ということも少なくありません。
企業において、1人の離脱が業務やチームに与える影響は大きく、早期の気づきと対応が何よりも重要です。
本コラムでは、5月に人材の離脱が増える背景をひも解きながら、実務の中でできる対策や取り組みを紹介します。組織の安定と働きやすさを両立させるためのヒントとして、参考にしていただければ幸いです。
5月に離職・休職が増える理由
毎年5月は、退職や休職の相談が増える傾向にあります。特に近年では、新入社員が退職代行サービスを利用して早期に離職するケースが増加しています。
退職代行サービス「モームリ」を管理する株式会社アルバトロスの2024年度のデータによれば、新卒社員による退職代行サービスの利用者数は5月が最も多く298名にのぼりました。次いで4月が256名、6月が251名と続いており、入社から4か月以内の利用が全体の約50%を占めています。
背景にあるのは、入社前の期待と実際の業務内容や労働条件とのギャップです。「入社前の契約内容・労働条件と勤務実態の乖離」が、4〜6月に退職代行を利用した新卒社員の約半数の退職理由となっています。
参考:退職代行モームリ2024年度新卒1,814名分の最新退職データを公開
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000024.000103965.html
加えて、いわゆる「5月病」と呼ばれる心理的な落ち込みも、この時期の離職を後押しします。
医学的には適応障害やうつ病の初期段階とされるもので、環境の変化についていけず、連休で緊張が緩むことで気分の落ち込みや無気力感が表に出やすくなります。物事を悲観的に捉えるようになり、「なんとなくだるい」「やる気ができない」といった感情が強まり、結果的に退職という選択につながることもあります。
参考:テレビ愛知「GW明けは新卒社員の退職代行サービス利用が増加 背景にミスマッチや五月病、コロナ禍の影響も」
https://news.tv-aichi.co.jp/single.php?id=7106
また、ゴールデンウィークで心身に余裕ができたタイミングで、自分の状態や今後について見直す人も少なくありません。特に慎重で責任感の強い人ほど、悩みを抱え込み、周囲に相談できないまま自分の中で結論を出す傾向にあります。そのため、周囲からは何も問題がなかったように見えていた人が突然離職することがあります。
だからこそ、日常の中で早いうちに変化に気づくことが、離職・休職防止に向けた第一歩です。
中小企業における人材流出・離職のインパクト
1人の離職や休職が組織にもたらす影響は、単なる欠員の発生にとどまりません。特に、採用・育成にコストをかけた新入社員や若手人材の早期離脱は、企業にとって大きな損失です。
まず、経済的なダメージがあります。採用活動や入社後の研修・育成には多くの時間と費用がかかっています。新卒1人の採用から戦力化までにかかるコストは、100万円以上かかると言われており、早期離職となればこれらの投資を回収することができません。
さらに、休職者が出た場合、周囲の従業員の業務負担が増加し、それに伴う残業代などのコストもかかります。
内閣府の調査によると、メンタルヘルス等の理由による休職において、以下のようなコストが発生しています。
休職前の3か月間のフォローによるコスト:約99万円 休職期間中(6か月)のフォロー:約224万円 復職後3か月のフォロー:約99万円 |
つまり、メンタル面等の理由で1人の休職で発生する周囲の残業負担コストは約422万円にのぼります。また、こうした負担は金銭面だけではありません。チーム内の業務が偏ることで、既存社員の疲弊や不満、モチベーション低下につながるリスクがあります。
結果として、さらなる人材流出や職場全体のパフォーマンス低下につながる可能性もあるのです。
このように、人材の流出や休職は単なる1人の欠員では済まされず、組織全体の生産性とコスト構造に大きな影響を及ぼします。だからこそ、問題が顕在化する前に「不調の兆候」に気づき、早めに手を打つことが求められます。
参考:内閣府 男女共同参画局「企業におけるワーク・ライフ・バランス推進のメリットに関する調査研究」
https://www.gender.go.jp/kaigi/senmon/wlb/pdf/wlb-kigyoumeritto.pdf
従業員の変化を見逃す組織のリスク
従業員が離職や休職したあとで振り返ると、職場の様子に違和感があったことに気づく場合があります。組織コンサルティングUniposによれば、退職を検討中の人の共通点として、以前より元気がなくなり、周囲へ不満をこぼすことが増え、会議での発言も減っているなどの傾向が現れやすくなるとされています。
参考:Unipos HRコラム「退職する社員に共通する兆候とは?大切な社員を辞めさせないための対処法」
https://media.unipos.me/retired_employee
このようなサインが見過ごされる背景には、いくつかの要因があります。まず、現場が多忙であらゆる業務に手が回らないため、上司がメンバー全員の細かな変化を観察する余裕がなくなります。繁忙期や人手不足の状況では、目先のタスクをこなすことに集中してしまい、些細な異変に気づきにくくなります。
また、変化に気づいても声をかけづらいという心理的なハードルがあります。相手のプライベートに踏み込むのは難しく、失礼にあたるのではないか、気にしすぎだと思われるのではないかと考え、なかなか行動を起こせないこともあります。
さらに、本人が自身の不調に気づいていない場合もあります。何となくつらいと感じながらも言葉にできず、相談のきっかけをつかめないまま限界に達するケースです。こうした本人が見逃すほどの小さなサインは、当然、上司や同僚も見落としやすく、結果として休職や退職というかたちで顕在化してしまいます。
このように、わずかな変化が放置されるリスクは、どの組織にもあります。だからこそ、感覚や経験だけに頼らずに、変化を捉える仕組みや習慣を組織で確立し、変化に気づいた際に早期対応することが求められます。次章では、現場で無理なく始められる取り組みと、その効果を可視化する方法について紹介します。
対策:従業員の変化に気付くための仕組み作り
従業員の変化を早期に気づくためには、組織全体で大規模なシステムを導入するよりも、まずは現場単位で簡単に始められる仕組みづくりが重要です。たとえば特定の部署やチームで、日々の簡単なアンケートや短いヒアリングを習慣化し、従業員のコンディションを可視化する取り組みをスタートすることも1つの方法です。スモールスタートとすることで、短期間で浸透し、導入効果もすぐに可視化できます。
取り組みを始めたら、変化を定量的に記録し、データを蓄積することが大切です。主観的な個人の感覚や経験だけに頼ることなく、客観的なデータを毎週、毎月、継続的に収集し、スコアリングすることで可視化することができます。データを収集することで、部署ごとのコンディション比較や、季節ごとの変化などを把握できるため、その仕組みを全社展開する際の上層部への説明にも説得力が出ます。
これらの取り組みを支えるツールとしておすすめしたいのが、従業員エンゲージメント向上支援クラウドサービス「ここレポ」です。
ここレポは、毎日のミニサーベイとスマホカメラを使うAI表情分析によって、個人の心身の変化をデータ化します。管理画面ではチームごと、部署ごとにスコアが一覧表示されるため、導入時から数値データを把握することができます。スモールスタートで現場に導入しやすく、運用が軌道に乗った段階で全社展開する際にも手間がかからずに拡大できる点も魅力です。
ここレポを活用すれば、専門知識がなくても従業員1人ひとりの状況をリアルタイムで把握し、シンプルな操作でレポートの作成ができます。
たとえば、特定のチームのメンタルスコアが継続的に低下している状況をグラフで示すことで、上司はサポートの優先度を判断し、適切なタイミングでフォローアップすることができます。また、データに基づいた改善計画を立案することもでき、通常のコミュニケーションでは見落とされがちな小さな変化にも対応できます。
従業員の変化に気づくための仕組みづくりは組織の文化として定着させることが理想ですが、まずは現場単位で取り組みを始めてみてはいかがでしょうか?
ここレポは、スモールスタートから全社展開まで見据えたシステム設計と、スコアリング機能による効果検証ができるサービスとして、従業員のエンゲージメント向上を支援するパートナーになります。
【人事向け5月病対策】のまとめ
従業員のわずかな変化を早期に把握し、休職や離職を防ぐには、日々のコンディションを可視化することが重要です。ここレポは日々のサーベイとAI表情分析を組み合わせることで、心身の状態を数値化し、素早いケアを可能にします。
従業員の変化を可視化することで、上司や人事担当者は対象者に声をかけるタイミングを逃さず、孤立感やストレスを抱える従業員への迅速なフォローを実現することができます。
まずはチーム単位で利用し始め習慣化していくことで、最小限の負担で素早く効果の確認をすることができます。
さらに、一定期間運用で、チームごとのスコアや傾向が自動集計されるため、取り組みの効果をデータで把握することができます。
こうして従業員1人ひとりの状態を日常的に把握し、必要なときにすぐ対応できる体制を整えることで、組織全体のエンゲージメント向上や長期的な人材定着につながります。従業員が安心して働くことができれば、働きやすい職場文化が根づき、企業の成長にもつながるはずです。
鈴与シンワートの従業員エンゲージメント向上支援クラウドサービス「ここレポ」は、人事担当者に役立つ機能や業務サポートに力を入れています。お気軽にお問い合わせください。